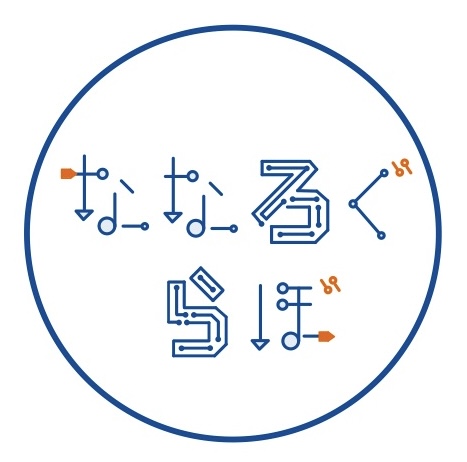お久しぶりです.仕事が多忙でしばらく更新が滞っていましたが,業務が少し落ち着いてきたため,また記事の更新を再開していきたいと思います.
次回からは ADC(Analog-to-Digital Converter:アナログ-デジタル変換器) をテーマに解説を始めます.本シリーズは,アナログ回路設計の基礎(MOSの動作や簡単な回路解析)を理解している方を主な対象としています.
筆者自身も業務でADCを扱った経験はありますが,正直なところ「知っているレベル」に留まっており,「本質的に理解しているレベル」にはまだ達していません.そこで本シリーズでは,勉強の備忘録として記事化しながら理解を深めていくことを目的としています.今後はADCに関するトピックをシリーズ化して整理していく予定です.
題材としては,IITK(Indian Institute of Technology Kanpur)の Solid-State Circuit Design (SSCD) Lab がYouTubeに公開している講義動画を取り上げます.これらの動画は,ADCのアナログ回路設計技術について非常に丁寧に解説されており,学習に最適です.筆者が動画を視聴して理解した内容を自分なりに噛み砕き,言葉に置き換えてまとめていきます.また,理解が難しかった部分や補足が必要な箇所については,以下の参考書籍を適宜引用する場合があります.
※なお,本記事は講義そのものの翻訳ではなく,筆者の理解を踏まえた解釈をまとめたアウトプットです.より深い理解を求める方は,元の講義動画や参考文献をご覧ください.
なぜADCを学ぶのか?
ADCはアナログ回路設計において非常に重要な要素です.情報化が加速する現代社会では,私たちの身の回りにある膨大なアナログ情報が,これまで以上にデジタルへと変換されることを求められています.
その一方で,アプリケーションごとにADCに求められる特性は異なります.
- 低消費電力
- 高速動作
- 高分解能
など,要求仕様に応じて直面する技術課題も多様です.これらを正しく理解し,アーキテクチャごとの性能トレードオフを把握することは,設計者にとって不可欠です.
本シリーズでは,ADCの基本技術を体系的に学びながら,設計上のポイントや課題意識を整理していくことを目標としています.ぜひ,筆者の勉強備忘録にしばしお付き合いいただければ幸いです.
参考リンク
- IIT Kanpur: https://www.iitk.ac.in
- SSCD Lab: https://iitk.ac.in/sscd
- 講義動画(YouTube): https://youtu.be/cI7bYpW7EvE?si=uhuL8tSMJan23LHf
参考書籍
- 『アナログ/デジタル変換入門 ― 原理と回路実装 ―』 和保孝夫(監)/コロナ社
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339009187 - 『ΔΣ型アナログ/デジタル変換器入門 第2版』 和保孝夫・安田彰(監訳)/丸善出版
https://www.maruzen-publishing.co.jp/book/b10120696.html